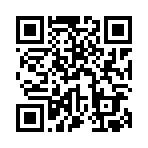2012年10月27日
明日の準備

1995年春 20代半ばで『推拿(すいな)』に出会い、魅せられ
現在、杵築で中国医学推拿整体小倉養生所を開いています
小倉一彦(おぐらいちひこ)です
公式HPはこちら⇒http://www6.plala.or.jp/ogura-youjou/
毎週日曜日は、午前10時から午後6時まで推拿塾の講義をやってます。
推拿塾の前後と昼休みは、施術の予約を取るので、
日曜日はかなりハードスケジュールです。
でも、もっとハードなのは、土曜!(の夜)
講義の準備をしなくてはなりません。
整体という仕事は、
開業することは法的にはあまり難しくありません。
大切なのは、開業してから“続けていくこと”なのです。
なので、うちの塾生たちは卒業後開業してからも講義には通ってくれます。
だいたい、1年半くらいの周期で同じ講義をやるのですが
その講義が2回目3回目の塾生もいるので
参加メンバーによって講義内容が少し変わったりします。
現在、杵築で中国医学推拿整体小倉養生所を開いています
小倉一彦(おぐらいちひこ)です
公式HPはこちら⇒http://www6.plala.or.jp/ogura-youjou/
毎週日曜日は、午前10時から午後6時まで推拿塾の講義をやってます。
推拿塾の前後と昼休みは、施術の予約を取るので、
日曜日はかなりハードスケジュールです。
でも、もっとハードなのは、土曜!(の夜)
講義の準備をしなくてはなりません。
整体という仕事は、
開業することは法的にはあまり難しくありません。
大切なのは、開業してから“続けていくこと”なのです。
なので、うちの塾生たちは卒業後開業してからも講義には通ってくれます。
だいたい、1年半くらいの周期で同じ講義をやるのですが
その講義が2回目3回目の塾生もいるので
参加メンバーによって講義内容が少し変わったりします。

そのために新しい資料を作ったり、塾生たちの旬な質問に答えれるよう
準備が必要なのです。
さて、明日の推拿塾ですが、
いよいよ理論推拿最後の講義です。
『顎関節症』と塾生からリクエストのあった『冷え症』についてです。
今、今日の施術が終了しました。
今日は杵築で観月祭があるので、今から娘二人をお茶会に連れて行って、
≪妻と息子はお茶会でお手前中≫
帰ってからご飯食べて、それからになりそう。
頑張って秋の夜長を満喫します。
≪息子にはなんでいっつも土曜の夜にまとめてするんね?
水曜くらいから少しづづすればいいやんといつも言われてますけど。。。
 ≫
≫
頑張ります。。。
2012年10月25日
推拿手法の話
はじめまして
1995年春 20代半ばで『推拿(すいな)』に出会い、魅せられ
現在、杵築で中国医学推拿整体小倉養生所を開いています
小倉一彦(おぐらいちひこ)です
現在、杵築で中国医学推拿整体小倉養生所を開いています
小倉一彦(おぐらいちひこ)です
ブログ、やった方がいいよねえと思いながらも
なかなか実行に移すことができませんでしたが、
本日ようやく重い腰を上げ、見よう見まねではじめようと思います。
“続けること”を第一に頑張りますので、皆さんどうぞ宜しく見守ってやって下さい。
推拿(すいな)、推拿(すいな)といっても
『推拿(すいな)とは何ぞや?』と思っている方がほとんどでしょう。
まずは、推拿についての簡単な説明から。
推拿とは、鍼灸、湯液(漢方薬)と並んで
中国の伝統医学(東洋医学の中国版)である中医学の三大治療法の一つで
体表にある経穴(ツボ)・経絡を中医学の理論にしたがって
独自の推拿手法で効率的に刺激することです。
そのことにより、全身をめぐる“気血”の流れがスムーズになり
身体の働きが活性化されて
自然治癒力が高まり、くずれていた身体のバランスが整うことで
身体の調子が回復していきます。
なかなか実行に移すことができませんでしたが、
本日ようやく重い腰を上げ、見よう見まねではじめようと思います。
“続けること”を第一に頑張りますので、皆さんどうぞ宜しく見守ってやって下さい。
推拿(すいな)、推拿(すいな)といっても
『推拿(すいな)とは何ぞや?』と思っている方がほとんどでしょう。
まずは、推拿についての簡単な説明から。
推拿とは、鍼灸、湯液(漢方薬)と並んで
中国の伝統医学(東洋医学の中国版)である中医学の三大治療法の一つで
体表にある経穴(ツボ)・経絡を中医学の理論にしたがって
独自の推拿手法で効率的に刺激することです。
そのことにより、全身をめぐる“気血”の流れがスムーズになり
身体の働きが活性化されて
自然治癒力が高まり、くずれていた身体のバランスが整うことで
身体の調子が回復していきます。

推拿で用いられる手技は、基本手技27種類
複合手技を含む応用手技になると500種類以上の手技があると言われています。
その中でも特に滾法(こんぽう)は、代表的な基本手技の一つであり
擺動類(はいどうるい)≪ゆらぎを基本とした刺激≫に属します。
滾法は1960年代上海で一指禅推拿流派の季峰原氏により考案されました。
滾法(こんぽう)の手技動作は
手関節の手背を捻転させながら連続的に手関節を屈伸・外転させることで
患部にリズミカルかつ有力な刺激を持続的に与え続けることができるという
非常に効果的でなおかつ効率のよい手技です。
複合手技を含む応用手技になると500種類以上の手技があると言われています。
その中でも特に滾法(こんぽう)は、代表的な基本手技の一つであり
擺動類(はいどうるい)≪ゆらぎを基本とした刺激≫に属します。
滾法は1960年代上海で一指禅推拿流派の季峰原氏により考案されました。
滾法(こんぽう)の手技動作は
手関節の手背を捻転させながら連続的に手関節を屈伸・外転させることで
患部にリズミカルかつ有力な刺激を持続的に与え続けることができるという
非常に効果的でなおかつ効率のよい手技です。

この“ゆらぎ”の刺激が被術者(推拿をしてもらう側)に癒しと安心を与え
気血の流れが活性化されます。
また、施術者(推拿をする側)にとっても、背部膀胱経や四肢などの
“使えるツボ”の多い部位に効果的に刺激を施すことができ
何時間操作しても疲れないという女性の治療家にもお勧めの手法です。
気血の流れが活性化されます。
また、施術者(推拿をする側)にとっても、背部膀胱経や四肢などの
“使えるツボ”の多い部位に効果的に刺激を施すことができ
何時間操作しても疲れないという女性の治療家にもお勧めの手法です。
小倉養生所は、中国における推拿医師養成の大学教育(各主要都市にある中医薬大学鍼灸推拿系)の主流を占める六大推拿流派の一つ、“滾法推拿流派”の流れを汲んでおり、滾法を中心に按揉法、一指禅推法等ゆらぎ系(擺動類)の手技を中心に施療します。
≪※滾法の滾の字は正しくは“さんずい”ではなく“てへん”です。≫